防衛大学校の制度や規律は厳しいことで知られていますが、その考え方はどこから来たのでしょうか?答えは防衛大学校初代校長である槙智雄に影響を与えた池田潔です。今回は池田潔が執筆した防大の見本となった学校(パブリックスクール)について述べられた『自由と規律 イギリスの学校生活』について紹介します。この本は岩波書店から出版されており防衛大学校入校前に配られる資料でも読むことが勧められています。
著者について
-1024x683.jpg)
著者の池田潔は中学卒業を待たずにイギリスにわたりリース・スクール(パブリックスクール)に3年、ケンブリッジ大学に5年、ハイデルベルク大学に3年間通いました。専門は英文学で1945年に慶応義塾大学の教授、1971年に同大学の名誉教授になっています。いわゆる防衛大学校の三恩人の一人で同門の槙智雄に大きな影響を与えています。その後は国家公安委員のメンバーとして活躍されています。著書は『自由と規律』のほかに『学生を思う』『少数派より』などです。
具体的な内容

内容を各章ごとにお話しします。
パブリック・スクールの本質と起源
この章ではイギリスに散らばるパブリックスクール全体の簡単な歴史が書かれており、注目されやすいオックスフォードやケムブリッヂ以外にもイギリスの支配階級層の教育を語る上で重要なものがあることを強調しています。それに絡めてイギリスの国民性や社会制度との関係も紹介されています。
その制度
この章ではイギリスの一般的な身分の人間が行くエレメンタリー・スクール、グラムマー・スクールや支配階級の人間の通う家庭教師、プレパレートリー・スクール、パブリックスクール、大学などの教育機関について全体的に述べられておりパブリックスクールがどのような立場にあるかを紹介しています。それに絡めてイギリスの教育全体の歴史やそれに関わってきた国家機関についても触れられています。
その生活
寮
このパートでは学生の普段の生活がどのようなものであったかが紹介されています。その中には防大の今は無き寒風摩擦につながるであろう彼らの習慣なども記されています。このパートは彼の体験談がふんだんに含まれており物語としても楽しむことが出来ます。特にパブリックスクールにおける飢餓道について述べられている部分は非常にユーモラスでした。
校長
校長はパブリックスクールにおいて絶大な権力を持っており『独裁者による善政』とも言われます。そのためパブリックスクールにおけるすべての事柄は校長の責任において行われていることが記されています。また、校長の役職にはどのような人物が就き何が求められどのようにパブリックスクール全体に影響を与えているかが述べられています。
ハウスマスターと教員
ハウスマスターは教員の中で選ばれ、各寮に専属し、学生の生活に責任を持つ先生の事です(スパイファミリーに登場するエレガントなヘンダーソン先生はセシル寮のハウスマスター)。この章では彼らの仕事や彼らがが学生に与える影響などが述べられています。後世に英語学を専門とする池田先生と当時の英語の先生との関係が非常に興味深いです。
学課
このパートではパブリックスクールの学課は日本における飛び級や留年がフレキシブルに行われていることが取り上げられています。また、積極的な授業や討論への参加が述べられています。パブリックスクールはノブリス・オブリージュを掲げており、有事には士官となる学生も少なくありません。そのため週に二回の軍事教練が行われておりその内容についても述べられています。
運動競技
イギリス人とスポーツというのは切っても切り離せないものでありパブリックスクールでも重要な要素になっています。彼らはスポーツを通してチームへの忠誠を知ることで国家への忠誠を学びます。このパートではパブリックスクール内でどのようなスポーツが行われているかを知ることが出来ます。
スポーツマンシップという事
パブリックスクールにおいて規律を身に着けるには運動競技が最も手っ取り早くその中でもスポーツマンシップが大きくかかわっています。実際のクリケットで起こったスポーツマンシップを象徴するような事件や、日常におけるスポーツマンシップの扱われ方等が描かれておりここでもイギリス人の国民性を垣間見ることが出来ます。
おすすめポイント

防大の規律の起源を知ることができる
冒頭でも申し上げた通り、防衛大学校の規律に関することは初代校長の槙智雄に影響を受けています。また槙智雄は慶應義塾の理事であり同門の教授である池田潔に大きく影響を受けています。そのため防衛大学校の寮生活や校友会などの生活は池田本人が経験したパブリックスクールの生活を見本に作られているのです。その名残を感じるものも多く防衛大学校といえば寒風摩擦を思い浮かべる人がいると思いますが、その由来となるものであろうパブリックスクールの習慣が紹介されています。ぜひぜひ本書を手に取って確認してみてください。
英国の紳士道・騎士道を知ることができる
防衛大学校に入るとしばしば聞くようになる言葉が「ノブリス・オブリージュ」です。この言葉は元々フランスの言葉で日本語では「高貴なるものの責任」と略されます。この言葉も英国の貴族のあるべき姿としてパブリックスクールの教育のモットーであり防衛大学校にも影響を与えています。その「ノブリス・オブリージュ」がパブリックスクールの学生にどのようにとらえられていたのか、学生にどのような影響を与えていたのかといったことを知ることが出来ます。
まとめ
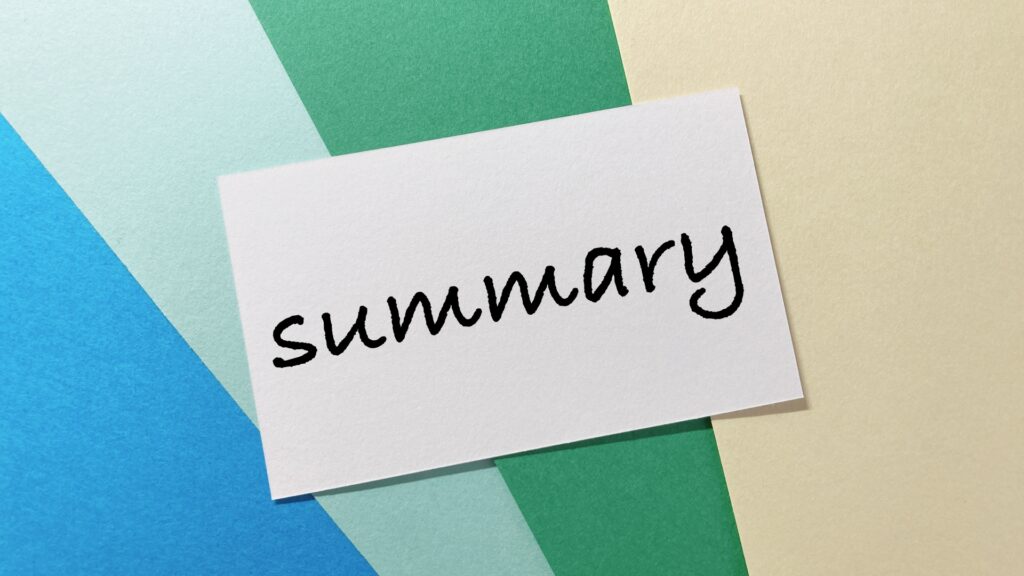
今回は『自由と規律 イギリスの学校生活』を紹介しました。この本は防衛大学校の見本となったパブリックスクールについてわかりやすく記されています。さらに池田先生の経験談がふんだんに混ぜ込まれており純粋な物語として楽しむことが出来ます。ぜひぜひ書店や古本屋で手に取ってみてはいかがでしょうか。ブックオフの購入ページは下にあります。
防大生であれば横須賀市の図書館で所蔵されているのでいつでも借りることが出来ます。質問・要望等あればこちらからお願いいたします。ではまた次の記事で
事後の行動にかかれ 分かれ

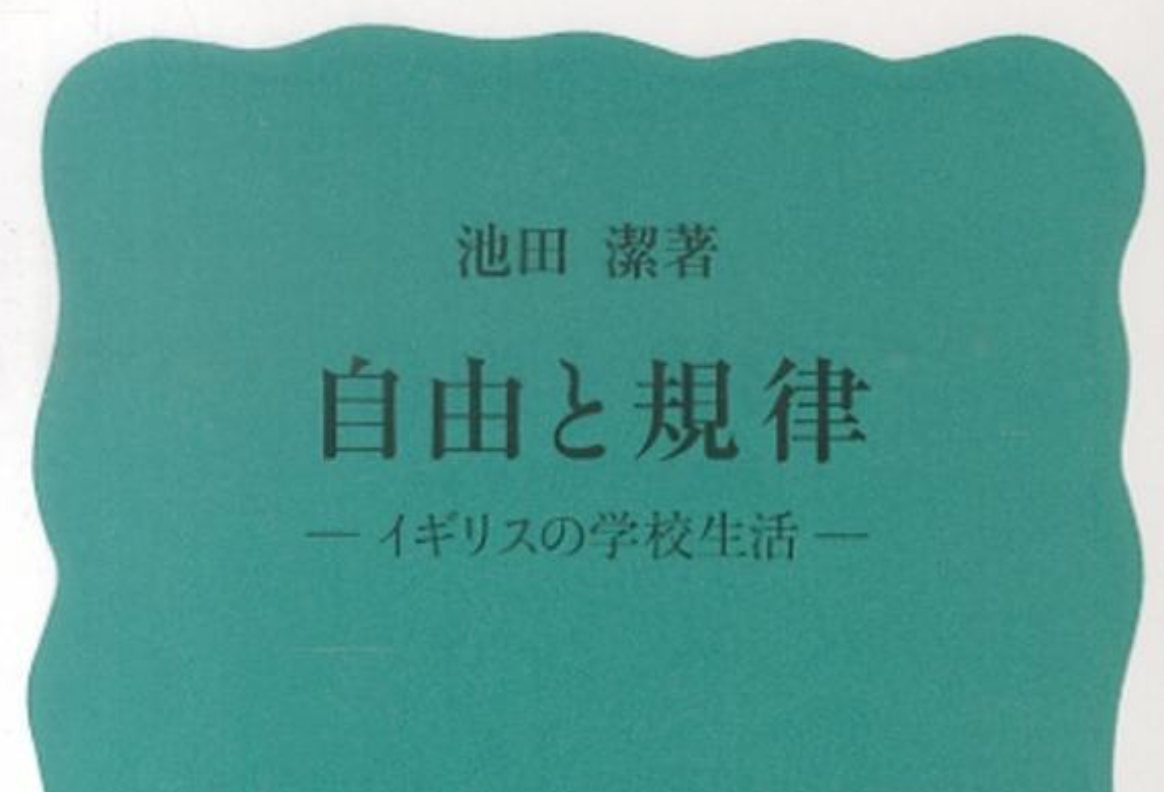



コメント